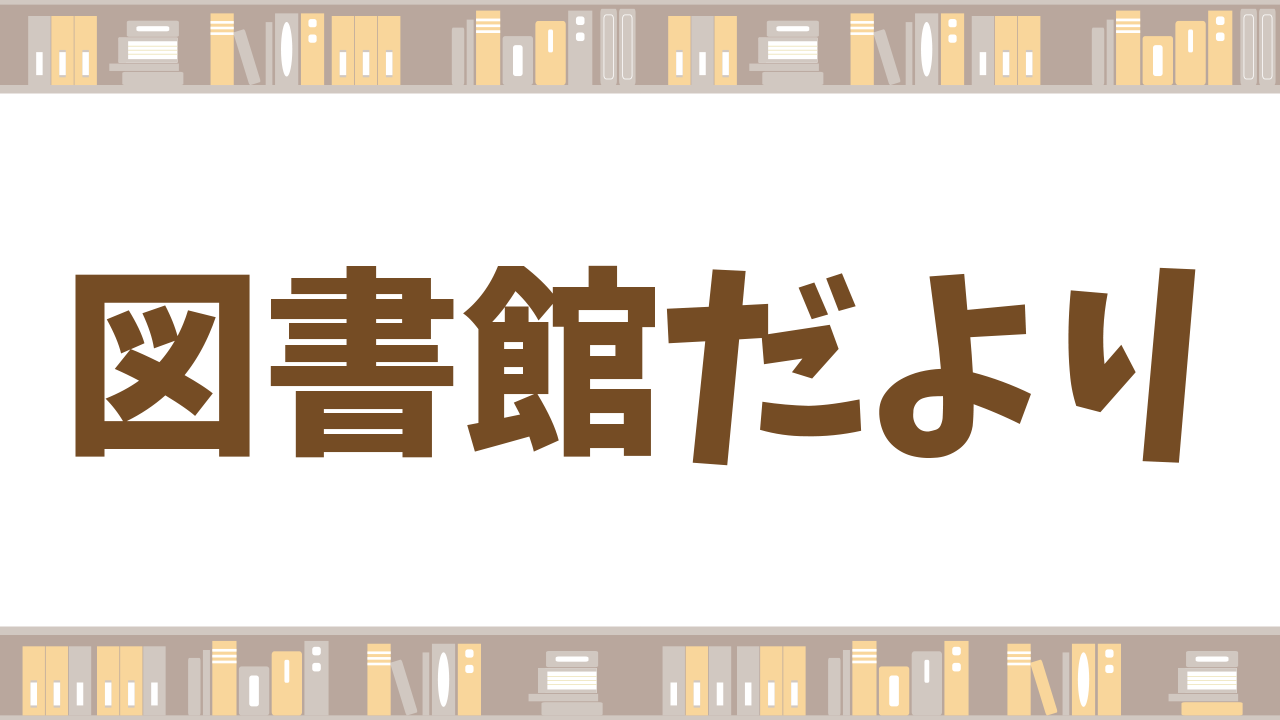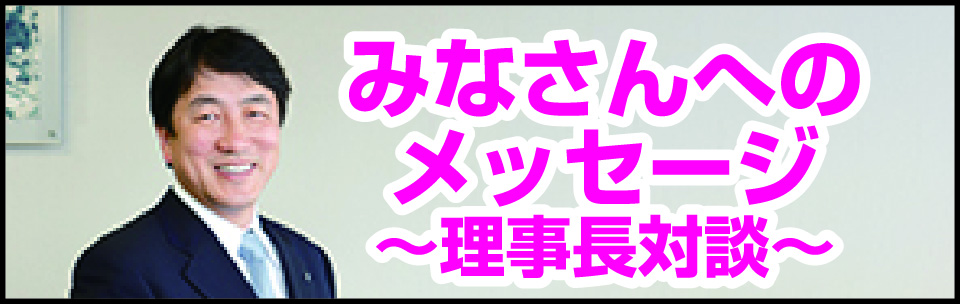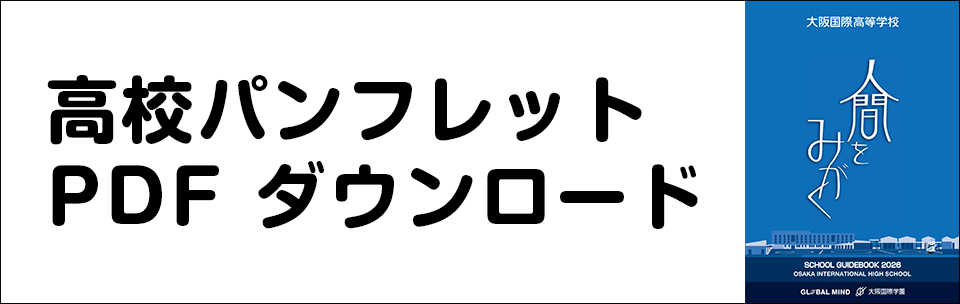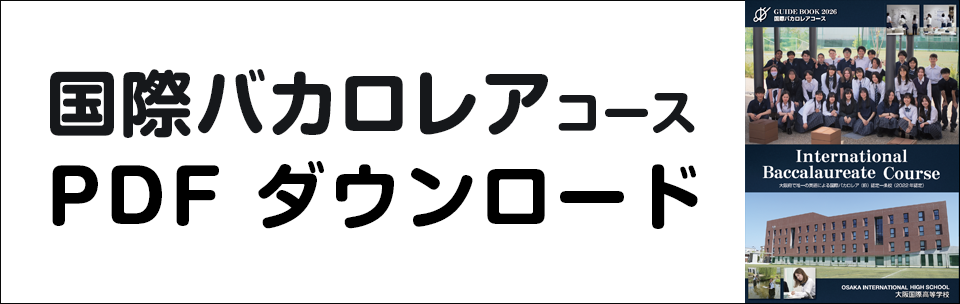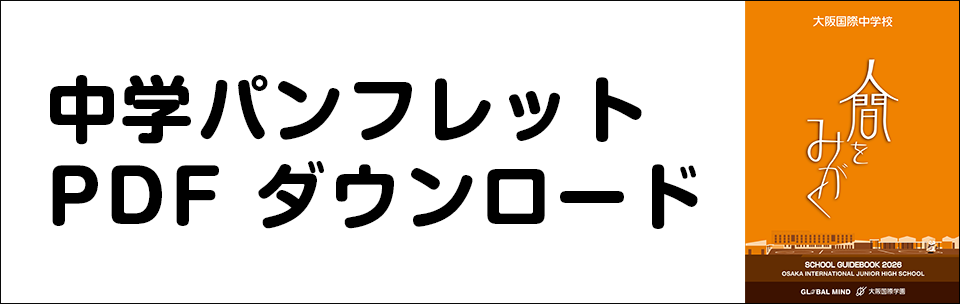真夏の太陽のもと、校庭を歩いてみました。この時期、咲いている花は意外と少ないですが、そんな中でも講堂近くに赤々と咲いている花があります。サルスベリです。サルスベリはとても花期が長いことで知られており、漢字で「百日紅」と書かれます。実際には一つの花が長く咲いているのではなく、それぞれの花が時期をずらして咲くことで、1本の木として花をつけている期間が長くなるということです。
サルスベリの花は結構ユニークな構造をしています。まず花弁(一般的にいうところの花びら)を見てみましょう。糸状にスラッと伸び、その先にフリフリに広がった構造をしたもの、これで1枚の花弁です。これが6枚あります。次に中心部の丸い構造から雌しべが1本、雄しべがたくさん伸びいてるのがわかります。よく見ると雄しべには2種類あります。内側には先の黄色い短い雄しべが多数あり、外側には長く内側に曲がった雄しべ(見た目は雌しべに似ています)が6本あります。内側の雄しべの数については、図鑑では40本前後とありましたが、実際に校庭の花3個について調べると、その数は32、35、37で、何らかの理由でそれまでに脱落したケースも考え合わせると、おおよそ40本というのが妥当な本数なのでしょう。
実は内側の雄しべは昆虫を引き付ける役目しか果たしておらず、受粉の役には立たないいわば「広告塔」の役目だけを果たしています。これに呼び寄せられたミツバチなどの昆虫の背中に外側の長い雄しべの先にある本物の花粉が付くことになります。外側の長い雄しべは内側にカーブし、呼び寄せられた昆虫の背中に当たる場所にちょうど葯がくるという、巧妙な位置関係にあります。何とも心憎い花の構造です。
【問題】光が強ければ強いほど植物は光合成をさかんに行うと考えていいのでしょうか?
光の強さを強くしていっても光合成速度がそれ以上大きくならない状態を光飽和といいます。さらに、高校生物では学習しませんが、強すぎる光はむしろ光合成速度を低下させることも明らかになっており、これを光阻害といいます。光阻害のメカニズムは複雑なので、少し触れるだけにしますが、植物が利用できる範囲を超えた余分な光エネルギーが活性酸素を発生させ、これがダメージとなる、といったところです。
植物にはこの光阻害を防ぐさまざまなしくみも備わっていることも知られています。真夏の強烈な日差しの中で花を咲かせているサルスベリも、きっと私たちと同じように日差しに耐えながら生きているのですね。
校庭の生きものたちへ、暑中お見舞い申し上げます。
【キーワード】 2種類の雄しべ 光飽和 光阻害