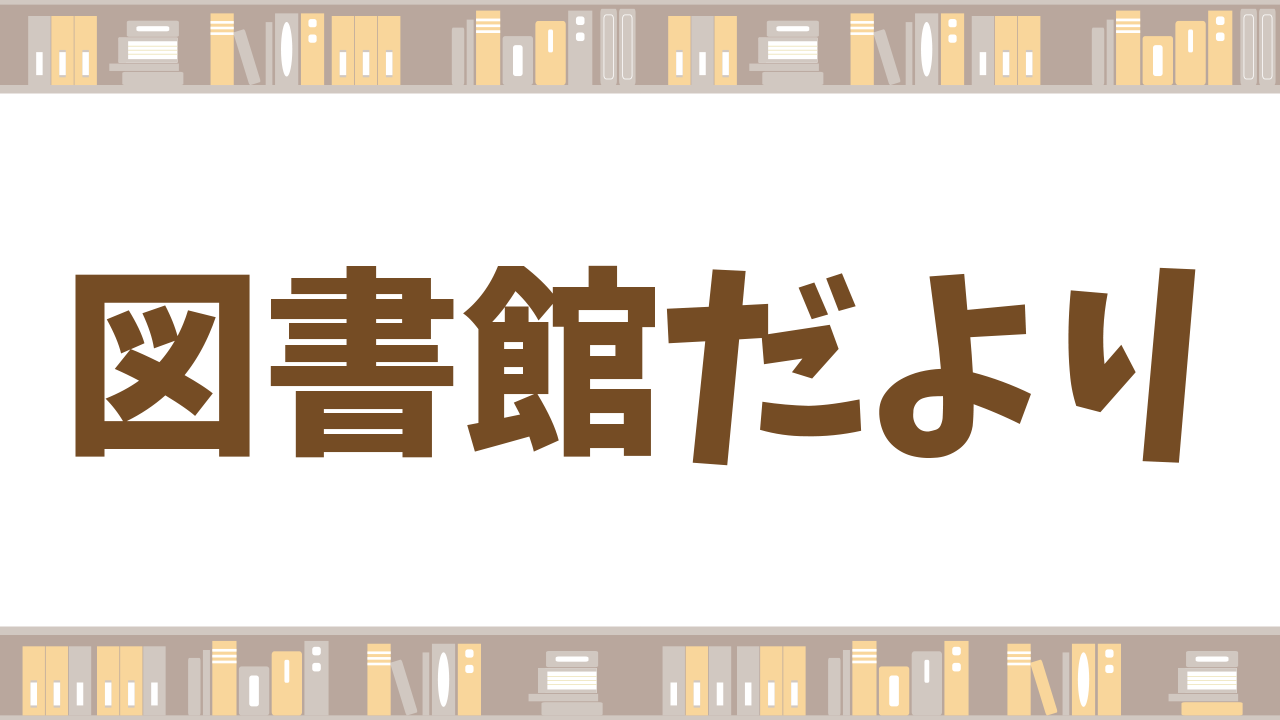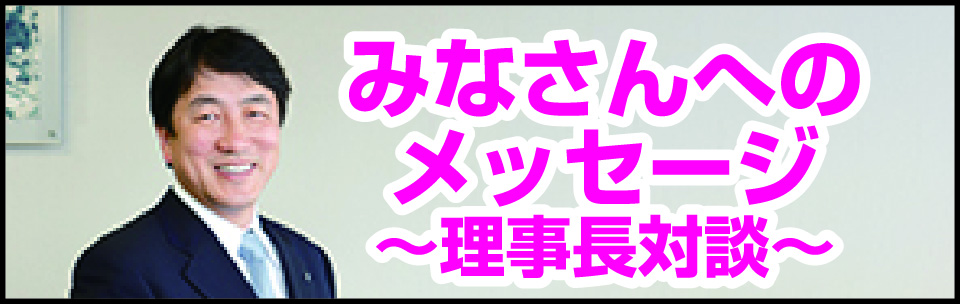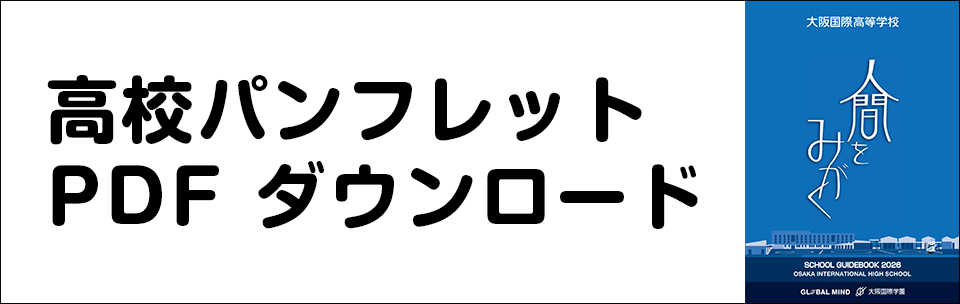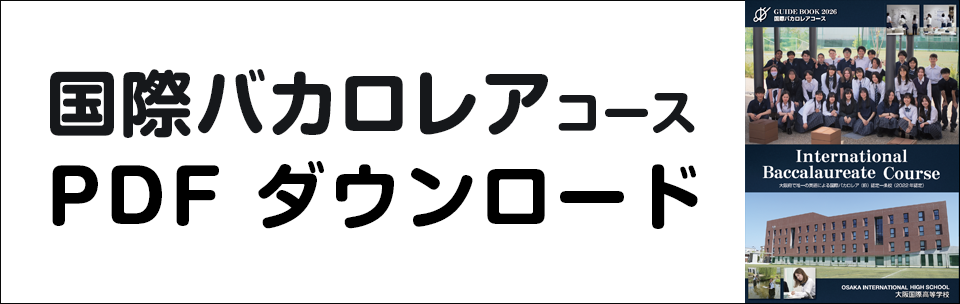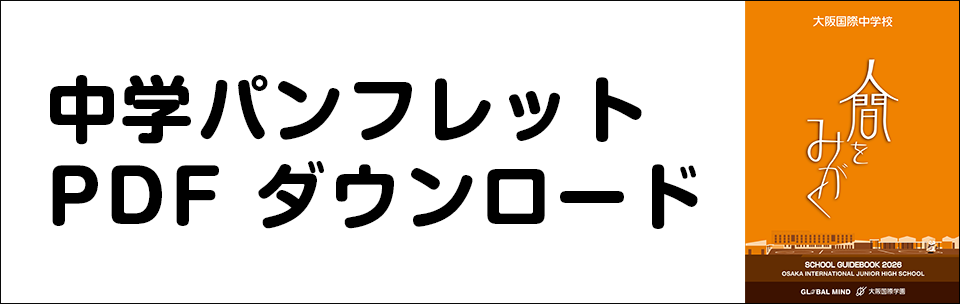美術室の天井に妙な昆虫が舞い込んでいるので、見に来てほしい、と言われ、見に行きました。遠目でわかりにくかったのですが、スズメバチのように危険のある種類でないことが明らかでした。気にしなくていいですよ、と言ったが、なにやら納得してもらえない雰囲気。どうやら、その昆虫がずっと同じ部屋の中にいることが気になって仕方ない様子。仕方ないので捕獲しました。「仕方なく捕獲した」という流れにしたかったのですが、生徒に「先生、何か嬉しそうやな。」と言われました。表情を読まれたか…。
この昆虫の正体はオオホシオナガバチ。大型で、非常に細長い体をしており、この個体がたまたま雌であったため長い産卵管を持っています。このあたりの特徴から見慣れない昆虫に見えたのは仕方なかったのかも知れません。
さて、このハチですが、いわゆる寄生バチです。雌個体は枯れ木などに潜んでいるキバチの幼虫などを探り当て、長い産卵管を使って、幼虫の体内に産卵するといいます。
【問題】 幼虫の体内に産み付けられた卵はその後どうなるのでしょうか?
生き物検索アプリ「BIOME」の説明によると、ハチ目(膜翅目)は大きく①ハバチ・キバチ類、②寄生バチ類、③有剣類に分かれるそうで、おおまかな進化の過程では①→②→③の順に現れたとされています。一般に寄生バチは他の昆虫に卵を産み付けるための細長い産卵管を持っています。産卵管には毒針の機能はありません。有剣類はこの産卵管を毒針という攻撃用に変化させたハチのなかまということです。もちろん毒針の本来の使用目的は獲物を仕留め、子に餌を供給するためのものであり、人を襲うために進化したものではありません。つまり、実際は人を刺すハチはハチのなかまのごく一部の種類だということです。意外なことに、ハチのなかまの過半数は寄生バチらしいです。
昨今、虫嫌いの生徒が増えているように感じます。その本当の理由が知りたいとずっと思っていました。その理由の一つに、昆虫という生き物が身近に居ないため、よく分からないというのが根底にあると感じています。確かに、人間誰でもよく知らないものを怖いと感じ、嫌いになるのはやむを得ないでしょう。しかし、昆虫も同じ地球に生きる仲間です。懸命に生きる昆虫たちの生きざまを知り、好きになれとは言わないまでも理解を示す人が少しで増えてくれたら、と思いながらこの文章を書きました。
【キーワード】 ハチ目(膜翅目) 産卵管 寄生 有剣類の毒針